片づけようと思っても、なかなかモノが手放せない。
そんなこと、ありませんか?
私も「もったいない」という言葉が頭の中にこだまして、まだ使える洋服、壊れていない食器、読みかけの本などを捨てることに強い罪悪感を感じていました。
「いつか使うかもしれない」「高かったし」「もらい物だし」
理由はいろいろ。
でも、その“いつか”はほとんど来ないんですよね。
今回は、もったいないと思ってしまう理由やどう対処したらいいのかご紹介したいと思います。
「もったいない」と感じる脳のしくみ
人間の脳は損失回避バイアスがあり、「得をする」よりも「損をしない」ことを重視するようにできています。
例えば、500円を得るよりも、500円を失うほうが強く記憶に残ります。
使わないけど捨てると「損した気分」になるのです。
「まだ使えるモノを捨てるのは損」と脳が認識し、「もったいない」と感じてしまうのです。
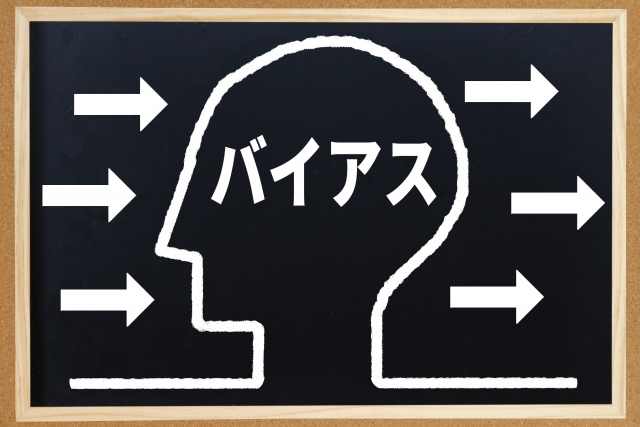
他にも、一度手に入れたものに、実際の価値以上の価値を感じてしまう心理があります。
同じマグカップでも、自分が持っているものは「なんとなく特別」。
誰かにもらったものは「思い出」や「感謝」と結びついて価値が上がる。
これにより、捨てることが自分の一部を失うように感じるのです。
日本特有の「もったいない文化」も影響

日本語の「もったいない」は単に「無駄」以上の意味があり、「モノを大切に」「自然や資源への感謝」などの精神的価値を含んでいます。
そのため、日本人は特に「もったいない」と感じやすい傾向にあるとも言われます。
モノを捨てることに罪悪感を感じるようにしみ込まれています。
昔はモノが少なく、大切に使われてきました。
しかし、現代はモノが溢れ、モノをため込むことで逆に心が散らかってしまって、ストレスの原因になります。
どうすれば”捨てられない”から抜け出せるの?

私も最初は捨てることへの罪悪感があり、モノがなかなか捨てられませんでした。
それでも思い切って捨ててみて、想像以上に心身スッキリしました。
と言っても、それなら捨てようと思う人は殆どいないと思います。
そこで、私がやってみた対処法・リセット思考法をご紹介します。
もったいないモノの中から、また買えるモノを1つ選んで思い切って捨ててみる。
捨てた後、本当に残しておけば良かったと後悔したら、同じモノを買う。
やってみると分かりますが、殆どのモノは買い直さないでしょう。
後悔したモノは買えばいいんだし・・・。
あと、思うのは「モノを使わないこと」こそ“もったいない”と思いませんか?
モノは使ってこそ活かされるのです。
もったいないと思う執着を手放してみると、心身軽くなった自分に気づくかもしれませんよ。



コメント